国保組合からの給付
窓口負担を限度額
までに抑えたいとき
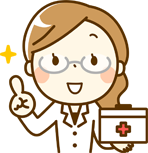
マイナ保険証や限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証よる負担抑制
入院や外来で医療費が多くかかる場合に、マイナ保険証を利用する、又は資格確認書と一緒に限度額適用認定証等を保険医療機関等の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。また住民税非課税の方は、あわせて入院時の食事代も軽減されます。
なお、自己負担限度額は所得によって決まります。詳しくは自己負担限度額の表をご覧ください。
マイナ保険証による窓口負担の抑制とは
ただし、次に該当する場合は当国保組合に申請手続きが必要となります。
限度額適用認定証等による窓口負担の抑制とは
申請手続き(申請先は所属の支部です)
- ※ 手続きには、組合員と対象者のマイナンバーの記入と本人確認書類が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
当国保組合の被保険者であることがわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルに表示される健康保険証の資格情報)、印かんの他に必要な書類
- ① 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第44号)
- ② 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
- ③ 雇用保険受給資格証のコピー(ハローワークから特定受給資格者及び特定理由離職者として受給資格証の交付を受けている方がいる場合のみ)
- *所得区分の判定は、マイナンバーによる情報連携により所得課税情報を取得して行います。情報が取得できない場合は、「所得がわかる書類(市区町村発行の所得課税証明書等)」の提出をお願いし、提出期限までに「所得がわかる書類」が提出されなかった場合は、一番高い所得区分で判定します。
- *住民税非課税世帯(「オ」または「低所得Ⅱ」)で過去12か月の入院日数が90日(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間に限ります)を超えている場合は、上記①のほかに入院期間を証明する書類(領収書のコピー等)が必要です。
![]()
- ア 対象となるのは、医療機関、薬局、指定訪問看護事業者で受けた保険診療です。接骨院・整骨院、鍼灸院、あんまマッサージは対象とはなりません。
- イ 70歳以上で、所得区分が「現役並み所得Ⅲ」又は「一般」の方は、この申請は必要ありません。これは、資格確認書と一緒に「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示するだけで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるからです。
- ウ 申請手続きの詳細は、所属の支部へお問い合わせください。